音階と役割の話~楽器が弾けなくても楽譜が読めなくても出来る!理論からの作曲!~
皆さんこんにちは。
講師の大西です。
本日からは「楽器が弾けなくても楽譜が読めなくても出来る!理論からの作曲!」を隔週で連載します。
以下は目次です。
一章:音階と役割の話
二章:マイナースケールの話
三章:コード進行の話(1)
四章:コード進行の話(2)
五章:コード進行のテクニック
六章:メロディの作り方
七章:転調について
八章:テンションコードについて
九章:裏コードについて
さて、本日は第一章の音階と役割の話をしましょう。
実は曲中で使える音というものは基本的には定められています。
どのような名前で定められているかというと、皆さんも聞いたことがあると思いますが「ハ長調」だったりとか「イ短調」であったりという「調」というもので決められています。
それぞれの調がどのような音で定められているかはいったん置いておいてまずは「ハ長調」の構成音から音階がどんな役割を持っているのかを確認しましょう。
まずはハ長調の構成音です。
皆さんご存知、「ドレミファソラシド」が構成音となります。
こちらは馴染み深い呼び方ですが実はイタリア語です。
ここでは深く解説しませんがこの先、和音について理解しなければならないとなったときに英名を知っておく必要があります。
ついでに和名との対応も知っておきましょう。
イタリア 英名 和名
—————————
ド C ハ
レ D ニ
ミ E ホ
ファ F ヘ
ソ G ト
ラ A イ
シ B ロ
このような形で対応しています
お気付きかもしれませんが「ハ長調」という言葉の「ハ」というのは音階から来ています。イタリア語で言うとドですね。
ここで前提知識として「半音上がると元の音に♯を付けくわえる」ということと「半音下がると元の音に♭を付け加える」ということを覚えておいてください。
例えばドの半音上はド♯(C♯)ですしミの半音下はミ♭(E♭)となります。
さて、音階というものは「基準音からどれだけ離れているかで役割が変わる」ようになっています。
まずはどのような役割があるのかを知りましょう。
与えられる役割は以下になります。
P=パーフェクト(完全)
m=マイナー(短)
M=メジャー(長)
dim=ディミニッシュ(減)
aug=オーギュメント(増)
カッコ内は和名になります
そして、以上4つの役割が以下の形で並びます。
(一つの差で半音階上がる)
P1(完全一度)
m2(短二度)
M2(長二度)
m3(以下、かっこなしは同じ様に数字が変わって名前がつけられる)
M3
P4
aug4(dim5)(増四度(減四度))
P5
m6
M6
m7
M7
P8~
以下同じように15まで続く
例えば基準の音がドだった場合は以下のように音が並びます。
役割 音階
—————————–
P1 ド
m2 レ♭
M2 レ
m3 ミ♭
M3 ミ
P4 ファ
aug4(dim5) ソ♭
P5 ソ
m6 ラ♭
M6 ラ
m7 シ♭
M7 シ
P8 ド
ここでハ長調の音だけを音の並びで残してみましょう。
役割 音階
—————————–
P1 ド
m2
M2 レ
m3
M3 ミ
P4 ファ
aug4(dim5)
P5 ソ
m6
M6 ラ
m7
M7 シ
P8 ド
になってつまりキー=C()ハ長調の音の並びは
役割 音階
—————————–
P1 ド
M2 レ
M3 ミ
P4 ファ
P5 ソ
M6 ラ
M7 シ
P8 ド
となります。
ハ長調の「ハ」という文字はドという意味でした。これは実は基準音がドという意味です。
つまり、上記の音階の中ではP1のことを指します。
そして、長調というのは基準音から
P1・M2・M3・P4・P5・M6・M7・P8
役割 音階
—————————–
P1 レ
M2 ミ
M3 ファ♯
P4 ソ
P5 ラ
M6 シ
M7 ド♯
となるので、レミファ♯ソラシド♯がイ長調の構成音となります。
ここで、長調という言葉の「長」というのは英名で「メジャー」といわれることを覚えておいてください。調は英名で「スケール」と呼ばれます。
つまり、ハ長調はCメジャースケール、イ長調はDメジャースケールというようにあらわすことが出来ます。
それに対して短調の「短」というのは英名で「マイナー」と言われます。
実は音楽の世界ではこのメジャーとマイナーの違いが非常に大事になってきます。
次回は、メジャースケールとマイナースケールの違いについて勉強していきましょう。
講師 大西優司

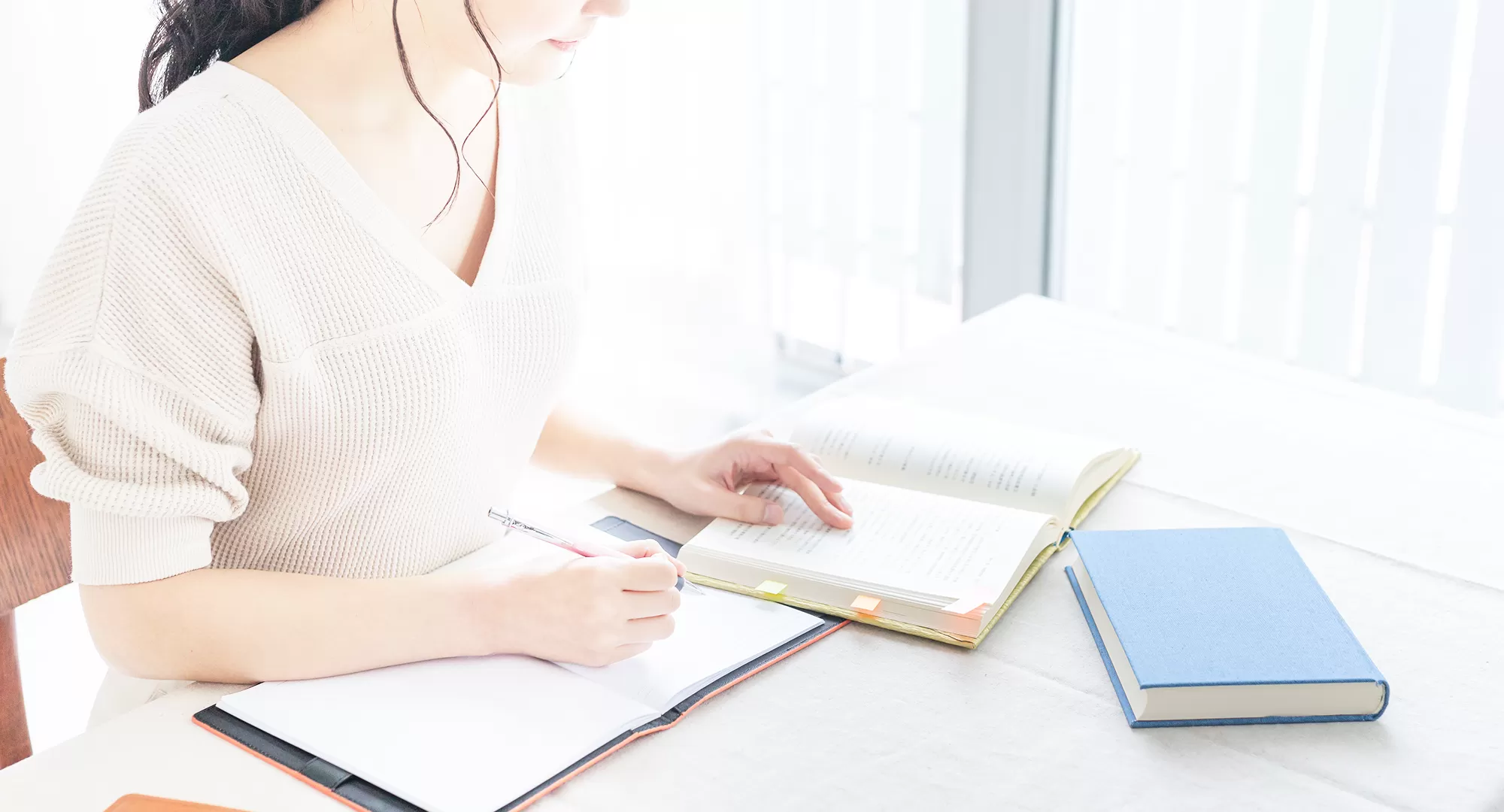
 LINE
LINE